| |
一宮 正和 顧問
|
| |
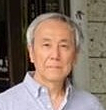
東京大学大学院研究科
原子力国際専攻特任研究員 |
1970年3月 |
徳島県立城南高校 卒業 |
| |
1974年3月 |
東京大学 原子力工学科卒業 |
| |
1976年3月
|
東京大学大 学院工学系研究科修士課程 修了
論文「3次元有限要素法による残留応力とK値の研究」 |
| |
| |
1979年3月
|
東京大学 大学院工学系研究科博士課程 修了
論文「熱衝撃破壊に関する研究」 |
| |
| |
1980年4月
|
旧動力炉・核燃料開発事業団
(現(独)日本原子力研究開発機構)入社 |
| |
| |
|
1998年10月 |
− プラント工学室長 |
| |
|
2003年4月 |
− システム技術開発部 次長 |
| |
|
2005年10月 |
− 次世代原子力研究開発部門 研究推進室長 |
| |
|
2009年4月 |
− FBRプラント工学研究センター長 |
| |
|
2012年4月 |
福井大学付属国際原子力工学研究所 客員教授 |
| |
|
2018年4月
ー現在 |
東京大学 大学院研究科原子力子国際専攻特任研究員 |
| |
● 主な研究業績 |
|
| |
高速炉の設計研究 |
| |
高温構造設計 |
| |
原子炉構造設計 |
| |
構造健全性評価 |
| |
計算力学(有限要素法、粒子法) |
| |
●現在のテーマと興味の対象 |
| |
計算力学、特に粒子法の開発 |
| |
過大地震下における構造健全性評価技術の開発 |
| |
●開催可能な講習会テーマ |
| |
計算力学、特に粒子法 |
|
| |
堀江 知義 顧問 |
| |

九州工業大学
名誉教授,非常勤講師 |
1977年3月 |
東京大学 工学部原子力工学科 卒業 |
| |
1979年3月
|
東京大学 大学院工学系研究科原子力工学専攻修士課程 修了 |
| |
1982年3月
|
東京大学 大学院工学系研究科原子力工学専攻博士課程 修了(工学博士) |
| |
1982年4月 |
日本原子力研究所 那珂研究所 研究員 |
| |
1986年3月
―1987年3月 |
米国オークリッジ国立研究所(ORNL) 客員研究員
|
| |
1990年4月 |
九州工業大学 情報工学部機械システム工学科 助教授 |
| |
|
1998年5月-12月 |
ドイツ国立情報学研究所(GMD) 客員研究員 |
| |
|
2001年9月
|
九州工業大学 大学院情報工学研究院機械情報工学研究系 教授 |
| |
|
2010年4月
―2014年3月 |
− 副学長
|
| |
|
2019年3月 |
− 名誉教授 |
| |
|
2019年4月
|
− 非常勤講師
(応力解析の基礎,計算力学・演習,計算力学特論) |
| |
|
2019年10月
―2020年7月 |
− 産学官連携研究員
|
| |
● 主な研究業績 |
| |
- 抵抗スポット溶接中に生じる電流-熱-接触変形3連成現象の研究
抵抗スポット溶接中の鋼板接触面に生じている、電流、熱、接触変形の3つの現象の相互作用のメカニズムを解明した。
抵抗スポット溶接は広く普及している技術であるが、溶接条件と生成される溶融域の関係は経験的に論じられることが多く、実際に接触面で生じている現象は十分に捉えられていなかった。3連成解析により、接触面上の4つの領域の生成・消滅挙動、および電流、接触電気抵抗、発熱の3つのピークの動きにより溶融部が生成されていることを明らかにした。
このメカニズムを考慮して3枚重ね溶接の条件比較を行った業績により、平成29年度の溶接学会論文賞を受賞した。さらに、この成果を応用したリングプロジェクション溶接法の開発で、令和元年の素形材産業技術賞を受賞した。
- 磁気減衰現象および連成解析手法に関する研究
構造物の振動と誘導電流の連成による磁気減衰現象を解析する手法として、一体型の連成解析手法を開発・提案し、この様な強連成現象を安定かつ高精度に解析できることを実証した。
従来の解析では2つの現象を交互に解析する分離型解法が使用され、数値的な不安定の生じない範囲で解析が行われていたが、本方法により、強磁場中の連成の非常に強い条件でも磁気減衰現象のシミュレーションを可能にした。同時に、連成固有モードや連成固有値に基づく評価パラメータを導出し、この現象の各物理パラメータへの依存特性を明らかにした。また、各分離型解法の数値的不安定性の発生条件を明確に表現した。
電磁場国際ベンチマーク解析(TEAM)に参加し、問題16の解析において本手法が高精度かつ安定であることが確認された。
- 核融合炉プラズマ対向機器の寿命評価に関する研究
炉心プラズマに面する機器について、実荷重および実形状モデルの寿命評価解析を行い、機器寿命に及ぼす各寿命因子の影響を明らかにした。
従来は理論式と単純形状モデルに基づく寿命評価が行われていたが、非線形有限要素解析による実形状、実荷重に基づく評価を導入し、各寿命因子が及ぼす相乗効果の重要性、および評価方法の重要性を示した。
この成果は、国際原子力機関(IAEA)によるプラズマ対向機器寿命評価ベンチマーク解析において有効性が確認され、臨界プラズマ試験装置(JT-60U)や国際熱核融合実験炉(ITER)のプラズマ対向機器設計に影響を与えた。
|
| |
●現在のテーマと興味の対象 |
| |
- 航空機用CFRP材の高周波誘導加熱による融着解析
- 構造・電流・熱・流体などの多くの現象が連成するシステムの力学
- 異なる解析ソルバーを組み合わせた連成解析の実現
|
| |
●開催可能な講習会テーマ |
| |
|
|
| |
和田 義孝 顧問 |
| |

近畿大学 理工学部
機械工学科 教授
|
1993年3月 |
東京理科大学 理工学部 機械工学科 卒業 |
| |
1995年3月 |
東京理科大学 理工学研究科 機械工学専攻 修士課程 修了 |
| |
1997年3月 |
東京大学 工学系研究科 システム量子工学専攻 退学 |
| |
1997年4月
|
東京大学大学院工学系研究科 助手 |
| |
2000年2月
|
財団法人 高度情報科学技術研究機構 招聘研究員 |
| |
2001年4月 |
− 研究員 |
| |
2002年4月 |
諏訪東京理科大学 システム工学部 講師 |
| |
2007年4月 |
− 准教授 |
| |
|
2012年4月 |
近畿大学 理工学部機械工学科 准教授 |
| |
|
2017年4月
-現在 |
− 教授
|
| |
● 主な研究業績 |
| |
- 疲労き裂進展シミュレーション手法の開発
- き裂のメッシュ生成手法に関する体系的研究
- 深層学習を用いたCAEサロゲートの構築とデータ拡張に関する研究
- 非接触全視野ひずみ計測手法の開発
|
| |
●現在のテーマと興味の対象 |
| |
き裂進展数値解析を通じてき裂進展則の高度化および提案を行っている。また、2016年より深層学習でき裂進展は予測できるか、学習の高速化に関する研究を実施。特にシミュレーションレスに向けたCAEサロゲートモデルの構築に関する研究をテーマとしている。
キーワード:計算力学(自動モデル生成、有限要素シミュレーション)、破壊力学、非接触ひずみ計測、
深層学習の工学応用
|
| |
●開催可能な講習会テーマ |
| |
- き裂進展シミュレーションと破壊力学
- 設計・工学問題に生かす機械学習・深層学習
|
|
| |
荒川 深映 テクニカルフェロー |
|

早稲田大学 先進理工学研究科 物理学及応用物理学専攻/博士課程 入学予定
|
2023年3月 |
早稲田大学 先進理工学部 応用物理学科 卒業 |
| |
2025年3月 |
早稲田大学 先進理工学研究科 物理学及応用物理学専攻 修士課程 修了 |
| |
2025年2月 |
フィンランド Aalto University 訪問研究員 |
| |
2025年4月
|
早稲田大学 先進理工学研究科 物理学及応用物理学専攻 博士課程 入学予定 |
| |
● 主な研究業績 |
| |
- 画像生成拡散確率モデルのパッチ単位生成によるメモリ消費量削減
- 拡散確率モデルを用いた任意解像度画像生成技術の開発
|
| |
●現在のテーマと興味の対象 |
| |
- 「拡散モデルに関する画像生成技術を信号処理の側面から見直す研究」
Stable DiffusionやDALL-Eを代表とする画像生成アプリケーションが、近年注目を浴びています。これらの基礎となっているのが拡散モデルと呼ばれる技術です。拡散モデルは、ランダムに抽出したノイズに対し、ニューラルネットワークを用いたノイズ除去を繰り返すことでデータ分布を復元する技術です。
このニューラルネットワークは平行移動等価性が欠如しており、入力画像を平行移動させると出力画像が大きく変化してしまい、ピクセルの位置と画像表現が縺れているという問題が存在します。そこで、厳密な平行移動等価性を保持するためのネットワーク設計や、エイリアシングを生じさせないためのモデル設計に関する研究に取り組んでいます。
- 「動画生成モデルを用いた三次元都市モデルの高精度再構成」
三次元都市モデルは、自動運転のテスト環境や防災・都市設計のシミュレーション環境としてなど、様々な分野で応用されるインフラとなりつつあります。しかし、その構築には高密度に収集したデータが必要であり、膨大な収集コストが必要です。そこで、大規模な動画データで学習された動画生成モデルが暗黙的に三次元構造を理解しているという考察から、三次元都市モデルの再構成に動画生成モデルを利用する研究を推し進めています。
|